
Sustty編集部がお届けするSDGs情報です。

日頃から海のお魚を食べているわけだし、海藻とかも大好きだから、SDGs14の達成に向けて、何かできることをやりたいなあ。
でも具体的に、できることはなんなんだろう?
こんな疑問に答えます。
この記事を書く私は、社会人になってからSDGs関連、環境関連の活動を続けている社会活動家です。
最近、海沿いに暮らし始めたこともあり、綺麗な海に癒される日々を過ごしています。そのこともあって、綺麗な海を後世に繋げていきたいものだと考えています。
SDGs14の目標達成に向けて、私たちにできることは無限にあります。ただ、全てに取り組むことはできないと思うので、SDGs14の目標達成に焦点をあてた上でのおすすめの「私たちにできること」は以下のとおりです。
✔︎SDGs14に対して私たちにできること
① 認定品の利用
② 海洋回復プログラムへの参加、寄付
③ 脱・二酸化炭素
でも、せっかく取り組むなら「なんで取り組むのか?」「なんでそのアクションが良いのか?」ということも知っておきたいですよね。
そこで本記事では、SDGs14の背景などを含めて「【今日からできる!】SDGs14「海の豊かさを守ろう」の達成に向けて私たちにできること」について紹介します。目標達成に向けて一人一人ができることを知り、今日からの取り組みに繋げてもらえたら嬉しいです。
目次
「SDGs14の私たちにできること」を考える前に知っておきたいこと

SDGsは「持続可能な開発目標」と定められているため、私たちにできることを考えるにあたって「持続性」に効果があるかを考える必要があります。
そのため、SDGs14に関する「持続可能性」とは何か?について紹介します。
SDGs14とは?
SDGs14とは「海の豊かさを守ろう」という目標のもと、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することを目的に作られました。
海は「食資源(お魚・海藻)、医薬品、燃料の天然資源、排出物/汚染物の分解・除去」など、私たちの生活からは切り離せない大切な自然です。
一方、人間の活動によって、その海が汚され、海の資源が致命的なダメージを受けつつあるため、持続的に海の豊かさを守る上でSDGs14が大事になります。
詳細については次の記事で紹介します。
関連記事:SDGs14とは?海の問題と「海の豊かさを守る」ための持続可能な開発目標
SDGs14のターゲット
SDGs14は「海の豊かさを守ろう」という目標を達成するために、7つのターゲットが設定されています。具体的には次のとおりです。
なお、文章が難解なため、「何をするのか?」という点について太の青字で示しています。
✔︎SDGs14のターゲット
| 14.1 | 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 |
| 14.2 | 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 |
| 14.3 | あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。 |
| 14.4 | 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 |
| 14.5 | 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 |
| 14.6 | 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。 |
| 14.7 | 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 |
| 14.a | 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 |
| 14.b | 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 |
| 14.c | 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。 |
参照:外務省
「SDGs14の私たちにできること」の取り組みポイント

SDGs14に取り組むにあたっては、上記に挙げられた7つのターゲットに効果的な取り組みができると、SDGs14の目標である「豊かな海を守ろう」の達成に貢献することができます。
そのため、これらターゲットから導かれるSDGs14に関する重要なポイントをおさえておきます。
✔︎SDGs14の取り組みポイント
① 海洋汚染への非加担
② 海洋生態系の「回復」への行動
③ 非酸性化対策
① 海洋汚染への非加担
SDGs14の私たちにできることのポイントの1つは「海洋汚染への非加担」です。
海は、生活排水や、各種ごみのが最終的に行き着く場所のため、普段の生活で無責任に放置されてしまうようなゴミは回り回って海洋の汚染に繋がります。
また、世の中には、海の資源を守るためへのさまざまな「認定」があります。認定の中には、海の生態系を様々な面で守ることを目的としたものが多く、そうした認定品を選ぶことで、海洋汚染への加担を減らすことができます。
逆を言うと、何も意識せず、非認定の製品や取り組みを選択していると、無意識のうちに海洋汚染に加担してしまうので、注意が必要です。
② 海洋生態系の「回復」への行動
SDGs14の私たちにできることのポイントの2つ目は「海洋生態系の『回復』への行動」です。
現状の私たちの生活、とその延長は「海洋生態系の破壊」がベースになってしまうほど、私たちのスタンダードな生活は便利に偏り、自然をないがしろにしてきました。そのため、特定の行動を「見直す」程度では海洋への影響は「ダメージの軽減」であり、「回復」にはなりません。
一方、すでに海洋は大きなダメージを受けているために「回復」に向けた積極的な行動が求められており、回復することにより、海洋の生態系に再度持続性を持たせ、未来にわたって共に生きていくことができるようになります。
③ 非酸性化対策
SDGs14の私たちにできることのポイントの3つ目は「非酸性化対策」です。
海洋が酸性化すると、当然その海洋系に住む生物にダメージを与え、微生物など海洋プランクトンの働きなども大きな影響を与えます。
「私は、海にお酢を流しているわけではないから、海洋の酸性化には加担していない」と感じるかもしれませんが、海洋の酸性化の原因の1つは「酸性雨」。つまり、雨が酸性になってしまうことも原因なのです。
では、なぜ雨が酸性になってしまうのか?それは人間活動によって排出される二酸化炭素(例えば、ガソリン、灯油の使用で生じる二)が水に溶けると酸性を示し、酸性雨に変えてしまいます。
海とは遠くに暮らしている人は、一見、海洋の酸性化に無関係のように感じますが、自然は複雑に関連しあっている例にもなりますが、陸に住む私たちの日常の行動が、海洋にダメージを与え続けてしまっているので、こうした対策もポイントになります。
SDGs14の私たちにできること

上で紹介したポイントを踏まえ、SDGs14の私たちにできることを紹介していきます!
✔︎SDGs14の私たちにできること
① 認定品の利用
② 海洋回復プログラムへの参加、寄付
③ 脱・二酸化炭素
① 認定品の利用
SDGs 14の私たちにできることの1つ目は「認定品の利用」です。
海洋製品には、いくつかの認定がありますが、その中でもメジャーで普及しているのが「MSCラベル」「ASCラベル」です。
MSCとは?
MSCとは、国際的な非営利団体「海洋管理協議会(Marine Stewardship Council)」の略称。
漁業における水産資源減少問題を解決していくことをミッションとし、水産物の認証である「MSCラベル」の発行等を行なっています。
MSCラベルとは「海のエコラベル」とも呼ばれ、水産資源や生態系に配慮した漁業による水産物の証で、対象は天然物のみ。厳正な環境規格をクリアした漁業で獲られた水産物にのみに与えられます。
ASCとは?
ASCとは、国際非営利団体「水産養殖管理協議会(Aquaculture Stewardship Council)」の略称。
海をはじめとする環境や地域社会に配慮した責任ある養殖とそれによって生産された水産物を対象とする認証制度の運営をし、「ASCマーク」の普及を実施しています。
ASCマークは、環境や社会に配慮した養殖場で生産された持続可能な水産物の証で、対象は養殖のみ。
大きな切り分けとしては、MSCは天然物、ASCは養殖物に対して、環境規格や生態系への配慮があるかを試験した認証ラベルになります。
最近では、イオンをはじめ、当ラベルの付いた製品を目にすることも増えてきているので、積極的に選択するようにしていきましょう。
また、認定ラベルをチェックするのは海洋資源だけではありません。「エコマーク」、「エコリーフ環境ラベル」や「環境保護印刷マーク」など、環境を汚さない管理をされた製品群を購入することで、汚染物質が最終的に行き着く海のダメージを経験することに繋がります。
海洋資源のための認証、MSCやASCに加え、環境全般にも視野を広げて、認証製品に気を掛け、選択していくようにしましょう。
② 海洋回復プログラムへの参加、寄付
SDGs 14の私たちにできることの2つ目は「海洋回復プログラムへの参加、寄付」です。
上で紹介のとおり、今のまま普通に過ごすだけでは、海洋へのダメージを「軽減」できますが、回復させることはできません。
海洋を回復させるにはある程度の労力をもって、回復に向けたアクションを起こすことが必要になります。
とはいえ、一人で海洋の回復に向けて行動するのも難しい場合もあります。そうした場合は、すでにある海洋回復プログラムに参加してみましょう。
各都道府県、またはNPOなどが海洋回復用のプログラムを実施しているので、アクセスしやすい場所からぜひ取り組んでみてください。
また、プログラムに参加するのが難しい場合には、プログラムを実施している団体への寄付を通して、貢献することもできます。
海の豊かさを回復させるために、アクションまたは寄付などをしてみましょう。
③ 脱・二酸化炭素
SDGs 14の私たちにできることの3つ目は「海洋の非酸性化の行動の選択」をすることです。
海が酸性化するのは、海に大気中の二酸化炭素が取り込まれる、または空気中の二酸化炭素が雨に吸収されて川から海に流れることが原因とされます。
そのため、海の酸性化を防ぐためには「二酸化炭素を出さない選択」をすることが大切です。
二酸化炭素は、私たちの日々の生活の中の至るところで生じてしまいます。
・ガソリン車の利用
・洗濯乾燥機の利用
・エレベーターの利用
これらはいずれも、意識すれは利用回数を減らす、または代替策で対応できる場合があります。
・ガソリン車利用→オンライン利用
・洗濯乾燥機利用→外に干す
・エレベーター利用→階段を使う
見回してみると、日々の生活の中で不用意に消費してしまっているエネルギーがあり、ついで二酸化炭素を発生し、海洋の酸性化を促進させてしまいます。
二酸化炭素を出さないことは、海の酸性化による被害を低減させることに有用なので、ぜひ試してみましょう!
なお、脱二酸化炭素の行動は、SDGs13(気候変動)とも関連が深いので、よかったら合わせてチェックしておきましょう。
関連記事:SDGs13とは?地球温暖化の問題と持続可能な開発目標「気候変動に具体的な対策を」
SDGs13以外にSDGs達成に向けて私たちにできること

このほか、SDGsに特化したSNS「Sustty」では、様々なSDGsの具体例を紹介しています。
1人1人の影響は小さいかもしれませんが、みんなが取り組むと「チリも積もれば山となる」で、大きな影響になります。
ぜひこれらの活動を参考に、世界を持続可能にしていきましょう!
また、Sustty-noteのサイトでは、SDGsに関わる様々な情報を掲載しています。宜しければぜひご参考にしてください。
Susttyの注目記事
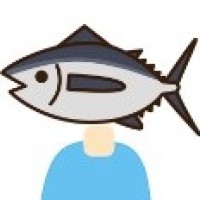
持続可能な未来の実現できる情報を発信しています。
・SDGsとは?
・気候変動の影響は?
・毎日どうやって過ごせば良いの?
2020年台は、今後の地球の持続性における分水嶺であり、この数年のアクションの変化が、今後の地球の住みやすさに劇的な変化をもたらします。
SDGs・気候変動・環境問題などを参考に「持続可能な社会」の参考にして頂けたら嬉しいです。






























